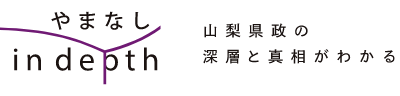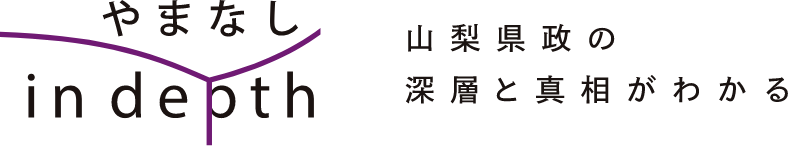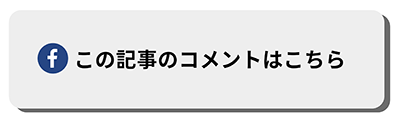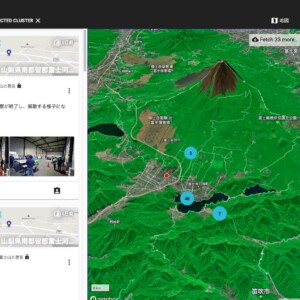小学校25人学級完成へ 実現の陰に企業局パワー
(連載:少人数教育 vol.1)
「25人学級」の対象が、2025年度以降、小学5、6年生まで順次拡充される。
だが、クラスを増やし、先生を増やすにはお金がかかる。
県独自の政策だから、国からのお金はあてにできない。
どこの自治体も厳しい財政事情の中で、実現が難しい「少人数学級」。
支えになったのは、何の縁もなさそうな水力発電事業だという不思議なストーリー。
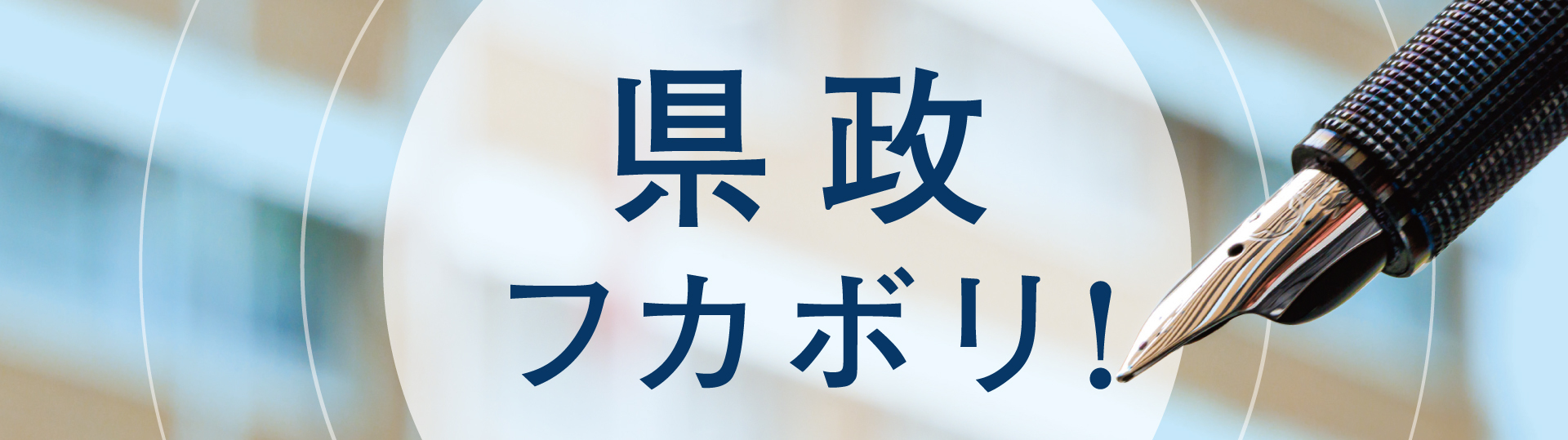
やまなしin depthでは、「県政フカボリ!」の新コーナーを始めます。
県が力を入れる重点施策をピックアップし、連載形式でその背景や課題、展望を県民の皆さまにお伝えしていきます。連載第一弾は「少人数教育の推進」です。
■この記事でわかること
✔ 山梨県では、水力発電事業の利益が独自財源として県民のための施策に充てられている
✔ 電力自由化がスタートして、競争市場への参入を果たし、県の電気はより高く売れるようになった
✔ 水力発電所を管理する現場の技術者たちは、絶壁のような階段を上がってメンテナンスを実施している
■おすすめ記事
・全国初の「25人学級」が誕生して1年。学校現場はいま
・世界をまたにかけて「山梨の先進技術を売る」
・公営企業として全国初のチャレンジ 「電力需給調整市場」に山梨県がなぜ参入?
県民に貢献する水力発電
2021年4月、県は全国初となる「25人学級」を小学1年生に導入した。少人数クラスにすることで、子ども一人ひとりへのきめ細かいサポートや、教師の負担軽減など、県の教育に大きな成果をもたらしている。
2024年11月、長崎幸太郎知事は2025年度以降にその対象を小学5、6年生まで拡大すると発表した。これまでは県の積立金を財源として活用してきたが、対象の拡大に伴って追加の財源確保が急務となった。
一体、どこからお金を持ってくるのか――。
山梨県企業局の齊藤雅司さんは「県の水力発電事業の利益から、2024年度は7億円の繰り出しを実施しました」と話す。
さらに、2025年度以降の3年間は毎年14億5千万円、総額43.5億円の繰り出しを計画しているという。
県の水力発電事業は戦後の電力不足の解消を目的として1957年から始まり、2024年現在は28カ所の水力発電所を運営している。供給電力量4.7億kWhは、山梨県内で使用される電力量の約8%、一般家庭約13万軒分にあたるという。
この電力を販売して得た利益が、「25人学級」のような取り組みにも活用されているのだ。

技術と英知の結晶で純利益が2倍に
県内の水力発電所でつくられた電気は、2009年度から2023年度まで、東京電力と15年間の長期契約を結んで販売していた。地道な料金交渉を重ね、販売価格は年々上がっていたものの、利益を大きく伸ばすには至らなかった。
しかし、2016年にターニングポイントがやってきた。電力自由化がスタートして、新規参入の電力会社にも販売することができるようになったのだ。競争市場になったことで、県の電気をもっと高く売れる可能性が出てきた。
齊藤さんは「2024年度からは売電入札の導入を決めていました。2020年頃から、どんな売り方をすれば一番収益を上げることができるのか、市場の調査研究を始めました」と話す。
売電市場の幅広いニーズに応えるため、供給電力量4.7億kWhを大・中・小に3分割して販売することにした。分割することで、多くの小売電気事業者が入札に参加しやすい環境になる。また、万が一、事業者が経営不振に陥ってしまったときのリスクも分散できる。
延べ13社が入札に参加し、最終的な売電収入の総額は約70億円になる。純利益は2023年度の15億5千万円から倍増し、約30億円になる見込みだ。
今回、繰出金として7億5千万円を増額することができたのも、齊藤さんたち企業局が利益を大きくする努力してきた成果だ。
しかし、齊藤さんは表情を引き締めてこう言った。
「根幹を支えているのは、現場の技術者たちです」
齊藤さんは「先人から受け継いだ水力発電の技術を守り、発展させていく“覚悟”を持ったプロフェッショナルたちが集まっているからこそ、成し得たことなんです」と強調する。
メンテナンスは秘境探検
水力発電は水が上から下に流れ落ちるときに発生する位置エネルギーを使って発電する。例えば早川水系であれば、南アルプスの山岳地形を生かし、河川から集めた水を発電所に流す水圧鉄管*は長さ500m、傾斜角度は50°だ。現場の技術者たちは、絶壁のような階段を上がって点検している。
*水力発電設備の水車に水を送る導水管


企業局の深沢一茂さんは、周囲から「発電所のドクター」とあだ名されるほどのベテラン技術者だ。入庁して38年間、水力発電のメンテナンスに携わってきた。深沢さんは「自分たちは普通に巡視路だと思っている道でも、他の人からは『崖を歩いている』と言われます。作業場に行くだけでも大変なんです」と苦笑しながら早川水系の水力発電所を案内してくれた。

水力発電所は山の中にある。その奥にある導水路や取水口などのメンテナンスには、さらに険しい道のりを越えて行かなければいけない。
「山中に引かれた5㎞の導水路は、真っ暗なトンネルです。ヘルメットにつけたライトで照らしながら、コンクリートのひび割れなどを歩いてチェックします。また、冬期は最奥にある野呂川発電所までの道が雪に埋もれてしまうため、職員が自ら大型特殊免許を取得して、除雪車を運転しています」(深沢さん)

自然災害に見舞われても、「自分たちでやる」!
水力発電は、自然災害のトラブルに見舞われることも少なくない。
深沢さんは、2011年9月の台風12号で黒河内取水口が被災したときのことを「一番大変だった」と振り返る。落ちてきた岩が取水口を塞いでしまい、まったく水が流れなくなってしまったのだ。
黒河内取水口は、事務所から車で20分、さらに歩いて1時間の場所にある。さまざまな土木業者に岩の撤去を依頼したが、「そんな困難な場所で、作業はできない」と断られた。
いつになっても引き受けてくれる業者は見つからなかった。ついに、しびれを切らした深沢さんが「自分たちでやろう」と声をあげた。周りの職員たちは「本当にやるんですか。冗談じゃないですよ」と戸惑う意見もあったが、みんなが深沢さんについてきた。
雪が降る中、岩にドリルで穴を空けて矢を打ち込み、ハンマーで少しずつ砕いていった。水に濡れた長靴で石の上に立ち止まっていると、あまりの寒さで靴底が張り付いてしまう。昼食や休憩時間も早々に切り上げて、黙々と作業を続けた。総勢23人の職員が力をあわせ、5日間で岩の撤去作業が完了した。


「業者に依頼している間は発電が止まってしまう。少しでも早く復旧させるためには、できる限り自分たちでやるしかないんです」(深沢さん)
水力発電が止まれば、その分収益も下がってしまう。そのため、深沢さんたちは、取水口が流木で塞がれていると聞けばチェーンソーを持って出動し、水圧鉄管から大量の水が噴き出したら全身びしょ濡れになりながら修復作業をする。そのマンパワーがあるからこそ、電力を安定的に供給することができる。

クリーンエネルギーにさらなる追い風
クリーンなエネルギーを生み出す水力発電には、さらなる追い風が吹いている。
2020年のカーボンニュートラル宣言や、「ウクライナショック」によるエネルギー価格の高騰が影響して、「水力発電を使いたい」という企業が増えてきたのだ。
そこで、2024年度から東京電力エナジーパートナーと共同で、県内外の環境意識の高い企業などにCO2フリー電気を供給する電気料金メニュー「シン・やまなしパワー」の運営を始めた。
特徴は「水力の電気料金」とは別に、「環境価値の料金」があることだ。「環境価値」とは、“うちは水力発電のCO2フリー電気を使っていますよ”という証明書のようなもの。
近年は、環境問題への意識が高い消費者や株主が多いのに加えてESG経営への指向も高まり、企業はこうしたクリーンな電気を求めている。「環境価値の料金」は、県内需要家には県外向けの半額以下*だ。県内企業ファーストな価格設定によって、県内企業の脱炭素経営を⽀援している。このような県の環境政策にも呼応して、大手化粧品メーカーのコーセー(東京都)が24年7月に南アルプス工場に着工した。
26年に稼働を予定しているコーセーの工場は、県の水素エネルギーを使って化粧品の製造を行う。さらに、県の水力発電と太陽光発電も使用する。
「国内で初めて、工場を建設する段階から水力発電の電気を使っています。県内に“100%CO2フリー電力の工場”が誕生すれば、山梨県が環境にクリーンなビジネス拠点としてさらに発展することができると期待しています」(齊藤さん)
*県内需要家には1.02円/kWh、県外需要家には2.31~3.3円/kWh
水素、DX、未来に向けて
企業局の水力発電事業は絶好調に思われる。しかし、齊藤さんは大きな課題もあると言う。
「深沢さんたちのような現場のプロフェッショナルたちはかなり気合が入ったメンバーです。近年は少子化などの影響もあり、メンテナンスや修理には辛い仕事も多く、採用募集してもなかなか人が集まりません。厳しい状況なんです……」
そこで、齊藤さんは水力発電事業のDX化を推進している。その一つがドローンの導入だ。
いまは水力発電所の保安管理に2種類のドローンを使った実証実験の最中だ。絶壁に沿って伸びる水圧鉄管の点検用と、遠くの水力発電施設内で飛ばして遠隔点検する二つの用途のドローンの導入を目指している。
齊藤さんは「ドローンの活用や業務のDX化の推進により作業を効率化し、現場職員たちの負担軽減につなげたい」と話す。

企業局は水力発電で培った経験を生かして、水素エネルギー関連の新事業にも挑戦している。米倉山(甲府市)において再⽣可能エネルギー電⼒からグリーン⽔素を作る P2G(Power to Gas)システムを開発し、国内外の工場への導⼊拡⼤に向けた取組を進めるなど「未来への投資」にも余念がない。
こうした企業局の活動をある学校が授業で取り上げた。韮崎市立甘利小学校だ。6年生が理科の授業(発電)について学ぶ際、やまなしin depthの取材内容をベースにした「探究学習」風の教材を用いたという。
授業を担当した甘利小の高瀬有治教頭と、小澤雄教諭は授業を受けた児童たちの反応について、口を揃えた。
「クリーンエネルギーの大切さ、そして点検やメンテナンスに職員の方々がどれほど心を砕いているか、まもなく中学生になる子どもたちなので、意外なほど理解が進んだ様子だった」
ある女子児童は、授業を受けた感想をこう書いた。
「水力発電の仕事はこんなにいそがしいということにおどろいた。収入したお金は、私たちのためにも使われていることを知った。ほかの人たちのためにがんばっていることに、感謝しています」
こんな子どもたちの声は、企業局のモチベーションにつながるだろうか。齊藤さんに聞いてみた。
「電気職の仕事は縁の下の力持ち的な存在であり、スポットライトが当てられることが少なかった。このような手紙をいただき、言葉では言い尽くせないほど嬉しく感じたました」
今後、企業局が目指す方向を尋ねてみた。
「企業局の3本柱は、100年続く水力発電事業の“持続”と、水素エネルギーなど新規領域への“挑戦”、そこで得た利益を活用して少人数許育の推進を含めた県民福祉の向上に“貢献”すること。それが私たちのやりがいなんです」
その淀みない答えに、“企業局の覚悟”が見えた。
※肩書きなどは取材当時のものです。
文・北島あや、写真・今村拓馬、山本倫子